
- 1 : 2025/02/28(金) 07:18:15.13 ID:+2dc2RTC0
-
マサバ「漁獲枠8割削減」でも資源回復とならない日本漁業、できるのにやらないリアルタイムで適切な資源管理、世界との大きな乖離
https://news.yahoo.co.jp/articles/b941a7fa51c1611fa501ae064a6137275c5552b1
- 2 : 2025/02/28(金) 07:18:47.41 ID:+2dc2RTC0
-
報道されていますが、マサバが獲れない状態が深刻化しています。水産庁が来シーズン(2025年7月~26年6月)の漁獲枠を8割減らすことも伝えられています。
筆者はこれまで、科学的データに基づいて何度も様々なWEB媒体で、「このままでは危険である」と指摘してきました。実際にいない魚をいると仮定して漁獲枠を設定してしまうと、結果的に幼魚まで一網打尽で獲り過ぎてしまいます。
世界では、国連食糧農業機関(FAO)に定められている「予防的アプローチ」に基づいて行動している国々の漁業が成長産業となっております。対照的に、現在の日本は予防どころか最後まで獲り尽くしてしまう傾向にあり、サバに限らず様々な魚が必然的に消えて行きます。そしてその理由が海水温上昇や外国漁船に責任転嫁される傾向が強くなっています。
筆者は北欧を主体に、長年国際的な水産業界と資源管理でつながっている唯一の日本人かも知れません。その視点からすると現在の資源管理制度は「異常」であり、獲り過ぎです。それを具体的に解説していきます。
改善のためには社会の理解と後押しが必要です。さもないと誤った処方箋で薬を飲み続ける状態が続き、後には水産資源ではなく負の遺産が残ってしまいます。
「漁獲枠削減」が意味なさない現状
日本人にとって身近な存在であるマサバ。そのマサバは、資源上2つの系統に分かれています。一つは太平洋で漁獲される太平洋系群で最も漁獲量が多い資源です。もう一つは、日本海~東シナ海にかけて漁獲される対馬暖流系群です。なお本文では、漁獲枠を国が定めるTAC(Total Allowable Catch=漁獲可能量)と同じ意味で記載しています。マサバの漁獲枠削減が報道されているのは、太平洋側で獲れるマサバ資源のことです。8割減というのは大きな数字です。しかしながら、もともとのマサバの資源量の評価が大きく、設定されていた漁獲枠が大きすぎて枠に対して漁獲量が大幅に少ないことが続いていたという面があります。
例えば2023年度のTACに対する漁獲実績はスルメイカもサンマも約2割です。TACを8割減らしても、これまで通りに漁獲できるということです。その間に資源量が減り漁獲量が減って行けばさらに形式的な内容になってしまいます。まさに「いたちごっこ」なのです。
それなのに報道では、「漁獲枠〇割削減!過去最低の漁獲枠!」となります。しかしながら、資源管理に影響もなく、ただ資源が凸凹を続けながら減り続けるだけなのです。
筆者は20年以上漁獲枠とにらめっこして、北欧などの最前線で買付をして日本向けに輸出してきました。獲り切れない漁獲枠は、乱獲につながってしまいます。何十年も北欧漁業の成功事例を見てきた立場からすると、100%失敗する漁獲枠の運用なのです。
漁獲枠の大きな削減以前に、資源量の実態に合った漁獲枠でなかったことが、本質的な問題でした。そのため、幼魚に至るまで過剰な漁獲が進み、サバが激減してしまったのに他なりません。
- 3 : 2025/02/28(金) 07:19:21.34 ID:+2dc2RTC0
-
漁獲枠が大きすぎるとどうなるのか?
サバの漁獲枠に限らず、実際の資源量が少ないのに獲り切れない漁獲枠が設定されてしまうとどうなるのか?漁業者の仕事は魚を獲ることです。資源が減って漁獲量が減ると供給量の減少に伴い単価が上昇します。本来はこの時点で、資源回復のため獲り過ぎないように漁獲量が制限されることが必要になります。
その際に漁獲枠が乱獲を防ぐ効果を発揮します。漁獲枠により、実際に漁獲できる量より少ない漁獲量に制限されれば、漁業者としては、価値が高い時期に価値が高い大きな魚を狙うようになります。価値が低い小さな魚は経済的にも資源的にも漁獲するのは良くないので自ら避ける努力をするようになります。ノルウェーでのサバ漁をはじめ、漁業を成長産業にしている北米・北欧・オセアニアなどの国々は、科学的根拠に基づく漁獲枠の設定で大成功しています。
一方で、日本の場合は漁獲枠が大きすぎるのが大問題です。漁獲枠が大きければこれまで通り漁獲ができますし、資源が減って魚が小さくなっていても魚価が上がっていますので、成長乱獲を起こしてしまう小さな魚でもできるだけ獲って水揚金額を上げようとします。なおこれは漁業者ではなく、資源管理制度の不備による問題です。
科学的根拠に基づかない資源管理の末路
筆者はWEB媒体などで採算にわたり、マサバ(太平洋系群)の資源評価が誤っており、まるで「埋蔵金」のようなサバ資源があるような内容になってしまっていることを指摘してきました。サバ資源があると主張する人たちは、1)マイワシがたくさんいるためにサバが深く潜っていて巻き網では届かず獲れない2)マイワシが多くてサバが寄り付けない3)サバは沖合(公海上)にいることを理由にしておりますが、これらはいずれも明確に誤りです。理由は1)巻き網船と同じ漁場で操業していた深場も曳けるロシアのトロール漁船の漁獲量も日本の漁船同様に漁獲量が減少している。2)マイワシはマサバのエサ。なぜエサに寄り付かないのか?サバの胃袋にはマイワシが入っているという漁業者からの報告が筆者にあります。また、マイワシが今よりはるかに獲れていた1980年代はマサバもたくさん獲れていた。マイワシが原因であれば当時はもっとサバが獲れていないはず。3)公海上でマサバを獲っていた中国漁船のサバ漁獲量も大きく減少している。
現実より資源量を多く見積もってしまう資源評価は、非現実的な漁獲枠設定の根拠となってしまい乱獲が進んでしまいます。これは漁業者が悪いのではありません。
上のグラフを見ていただくと、近年のマサバの漁獲量は1970年代より、はるかに少ないことがわかります。しかしながら修正前の資源評価では、70年代より、近年の方が資源量が多い評価になっていました。
結果として、少しわかりづらい説明になりますが、マサバ(太平洋系群)は2024年に過去の評価過大でTACを決める科学的根拠となる生物学的許容漁獲量(ABC)が35%引き下げられ、25年には、22年の資源量比(ゴマサバ含む)で65%引き下げられている。過大な漁獲枠が獲り過ぎを引き起こす「いたちごっこ」の結果を見せています。
以下ソース
- 4 : 2025/02/28(金) 07:19:50.84 ID:v3Wum2Psr
-
絶滅するまで取り尽くす
- 5 : 2025/02/28(金) 07:21:06.27 ID:82f2zKHjd
-
クジラが魚を食い尽くしてるんだぞ(迫真)
- 6 : 2025/02/28(金) 07:21:46.05 ID:5ef06b8J0
-
え待って、取れなくなる前に取らなきゃ!
- 7 : 2025/02/28(金) 07:23:53.34 ID:N9YjYUhb0
-
この記事書いた記者、自分が日本で一番水産資源の深刻さを理解している!みたいな事言っててアタオカ過ぎる
何様なん? - 10 : 2025/02/28(金) 07:26:09.08 ID:+2dc2RTC0
-
>>7
片野 歩(かたのあゆむ)
東京生まれ。早稲田大学卒。
2022年東洋経済オンラインでニューウェイブ賞受賞。
2015年水産物の持続可能性(サスティナビリティ)を議論する国際会議シーフードサミットで日本人初の最優秀賞を政策提言部門で受賞。
1990年より、最前線で北欧を主体とした水産物の買付業務に携わる。
特に世界第2位の輸出国として成長を続けているノルウェーには、20年以上、毎年訪問を続け、日本の水産業との違いを目の当たりにしてきた。
ノルウェー、デンマーク、アイスランドをはじめ発信に関心を持っている海外の水産関係者も多い。Pelagic Fish Forum, North Atlantic Seafood Forumなどからの依頼で世界で講演も行っている。
その違いを、ブログ「魚が消えて行く本当の理由」、Wedge ONLINE「日本の漁業 こうすれば復活できる」東洋経済オンラインで連載、書籍出版、大学での講義等で伝え、2020年に施行された70年振りと言われる改正漁業法を行った政治家にも影響を与えて来た。 科学的根拠に基づく問題点の整理と解決法の提示には、全国の漁業関係者や水産会社、高校生から政治家、行政、研究者と幅広い支持層を持つ。 - 8 : 2025/02/28(金) 07:24:11.35 ID:R4Hg2vJh0
-
食べて応援
- 9 : 2025/02/28(金) 07:25:37.10 ID:N9YjYUhb0
-
著者紹介
片野 歩
(かたの・あゆむ)
Fisk Japan
Fisk Japan。東京生まれ。早稲田大学卒。Youtube「おさかな研究所」発信。2015年水産物の持続可能性(サスティナビリティー)を議論する国際会議シーフードサミットで日本人初の最優秀賞を政策提言(Advocacy)部門で受賞。1990年より、最前線で北欧を主体とした水産物の買付業務に携わる。特に世界第2位の輸出国として成長を続けているノルウェーには、20年以上、毎年訪問を続け、日本の水産業との違いを目の当たりにしてきた。著書に『日本の水産資源管理』(慶應義塾大学出版会) 『日本の漁業が崩壊する本当の理由』、『魚はどこに消えた?』(ともにウェッジ)、『日本の水産業は復活できる!』(日本経済新聞出版社)、「ノルウェーの水産資源管理改革」(八田達夫・髙田眞著、『日本の農林水産業』<日本経済新聞出版社>所収)。 - 11 : 2025/02/28(金) 07:27:46.80 ID:lIb1w1Gt0
-
どうせジャップ密猟してる
- 12 : 2025/02/28(金) 07:28:56.24 ID:+yck85EM0
-
稚魚だけは絶対海に返す漁法とかできんもんかね
- 21 : 2025/02/28(金) 07:35:12.54 ID:+2dc2RTC0
-
>>12
しらすが食えなくなっちゃう😖水産資源保護の観点から見るとしらす干しや佃煮とかってかなりヤバい事やってんだよな
- 28 : 2025/02/28(金) 07:42:01.91 ID:5Q5XxaJo0
-
>>12
サイズで制限すると今度は小型のばかり生き残って魚が小型化する可能性とかもあるから
サイズじゃなく本当に稚魚だけとか出来ない限りは難しいかもね - 14 : 2025/02/28(金) 07:30:15.10 ID:75txK5p40
-
中国より酷いや
- 15 : 2025/02/28(金) 07:30:57.33 ID:wejhPqa+0
-
取り尽くせ!魚介資源!魚種交代!
- 16 : 2025/02/28(金) 07:31:30.24 ID:HUI7KOeW0
-
日本漁師が獲り過ぎて漁獲高が減ってんのに
◯バカジャップは全部中韓のせいにしてるというね
ここまで他責のアホ民族他におる?
恥晒しもいいとこだろ日本人であることが恥ずかしいわ - 17 : 2025/02/28(金) 07:31:49.59 ID:3P44uZVW0
-
食べて応援!
- 18 : 2025/02/28(金) 07:32:48.04 ID:0UCiIapkH
-
地獄の朝鮮カルト自・民統
- 19 : 2025/02/28(金) 07:34:48.35 ID:+IvakO9B0
-
日本で一番ヤバいのが漁業
いまならまだぎりぎりどうにかなるかもしれないけどやる気がないからな
四八酒場どころか三〇酒場になる勢いでヤバい - 20 : 2025/02/28(金) 07:35:02.95 ID:0vyEcRZb0
-
漁獲枠は前年実績値以下で設定しないと全部取っちまうぞ🥺
- 23 : 2025/02/28(金) 07:36:24.58 ID:vpnv+wSd0
-
取らないようにしてもチャイナに根こそぎ獲られてヘラヘラしながら見てるだけ
- 24 : 2025/02/28(金) 07:36:39.98 ID:aGxQO5Xe0
-
中韓台が取り過ぎてるんだろう
- 25 : 2025/02/28(金) 07:36:56.91 ID:r/E3RXVX0
-
養殖サバでいいじゃん
美味しいよ - 26 : 2025/02/28(金) 07:37:52.97 ID:aGxQO5Xe0
-
日本は悪くなんかないから
- 27 : 2025/02/28(金) 07:41:38.36 ID:d3W8b8Q+0
-
獲らないと誰かに獲られる
獲られる前に取り尽くせ - 29 : 2025/02/28(金) 07:42:15.04 ID:aGxQO5Xe0
-
日本は周辺国に恵まれないな、周りが乱獲国密漁国ばかりで
日本が本当に可哀相だ‥ - 30 : 2025/02/28(金) 07:42:25.34 ID:m89zSWIz0
-
身のりが悪い秋刀魚しか扱えないオンボロスーパーでも公平に毎日確保できて捌いたりの手間もかからず並べられるのがシラスなんよね🤤
- 31 : 2025/02/28(金) 07:43:49.94 ID:n5Sfl5qJ0
-
波止場のサビキ釣りでも数年前は釣れ方がサバ>アジだったけどここ2年連続してアジ>サバになってる
局地的なのかもしれんけど - 32 : 2025/02/28(金) 07:44:07.14 ID:01XNVq4K0
-
>現在の資源管理制度は「異常」であり、獲り過ぎです。
- 33 : 2025/02/28(金) 07:45:13.63 ID:znnhzmOI0
-
でも去年は久しぶりにサンマ豊漁って言ってたでしょ
本当に数が減ってたなら1年で一気に増えるのは不可能なんだから魚種交代理論がおそらく正しいよ
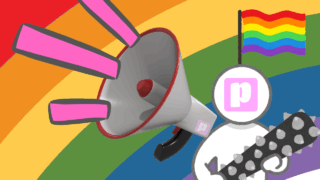


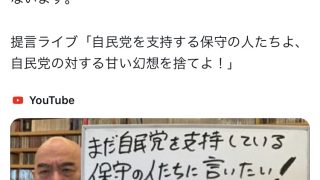

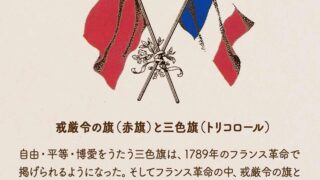







コメント